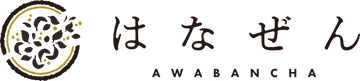阿波晩茶ができるまで
はなぜんの茶葉はなぜ割れているのか?
一般的に販売されている阿波晩茶は葉の形を保っていますが、はなぜんの阿波晩茶の茶葉は細かく砕いた状態で販売しています。
それには、大切な2つの理由が存在します。

理由1:機械乾燥による安全な仕上げ

従来、阿波晩茶の茶葉は天日干しによって乾燥させるのが一般的でした。しかし、天日干しではチリやホコリ、虫の混入といった衛生面の課題があり、品質を安定させることが難しくなります。
はなぜんでは、お客様に安心・安全な阿波晩茶をお届けするため、専用の機械乾燥を採用しています。機械乾燥を用いることで、異物の混入を防ぐだけでなく、温度や湿度を最適に管理し、茶葉の品質を一定に保つことができます。
はなぜんの阿波晩茶は、伝統の技法を大切にしながらも、現代の技術を活かし、より安心して楽しんでいただけるよう製造しています。
理由2:粉砕による豊かな風味の引き出し

阿波晩茶の風味を最大限に引き出すために、専用の粉砕機を使用し、茶葉を細かく砕く工程を取り入れています。これにより、茶葉の断面積が増え、お湯に触れる表面が広がることで、お茶の成分がより効率的に抽出されるようになります。
阿波晩茶の特徴である乳酸発酵によるまろやかな酸味や旨みを、しっかりと感じていただけるよう、最適なサイズに調整しています。また、茶葉が細かくなることで、お湯を注いだ際に短時間でしっかりと成分が抽出され、香り高く味わい深い阿波晩茶を手軽に楽しめるようになりました。
この粉砕工程は、従来の製法にはなかった現代の技術を活かした工夫のひとつです。伝統の味を守りながらも、より美味しく、より手軽に楽しめる阿波晩茶をお届けするため、はなぜんは細部にまでこだわり続けています。
阿波晩茶ができるまで

1.収穫

1.収穫
阿波晩茶の製造は、厳選された茶葉の収穫から始まります。阿波晩茶の茶葉は緑茶などに使われる新芽ではなく、成長した葉を使います。太陽の光を存分に浴び成長した茶葉は、発酵に適した成分を豊富に含んでおり、阿波晩茶特有の味わいを生み出す大切な原料となります。
摘み取られた茶葉は、すぐに次の工程へと移され、新鮮な状態を保ちながら加工が進められます。
ここから、阿波晩茶ならではの発酵の旅が始まります。
2.洗浄

2.洗浄
茶葉に付着した土やホコリを丁寧に取り除き、清潔な状態にすることが不可欠です。
はなぜんでは、衛生管理を徹底するために、専用の洗浄設備を使用し、大量の水と空気を送り込み茶葉をしっかりと洗います。泡立って見えるのは洗剤ではなく、空気によりできた泡となります。これにより、不純物を取り除くだけでなく、発酵の均一化にもつながり、茶葉本来の持つ香りや風味を損なわずに仕上げることができます。
この工程を経ることで、次の「茹で」の工程へスムーズに移行でき、より品質の高い阿波晩茶の製造へとつながります。
3.茹で

3.茹で
洗浄を終えた茶葉は、すぐに大釜で茹で上げる工程へと進みます。阿波晩茶の特徴である乳酸発酵は、この茹での工程があるからこそ実現できるものです。
茶葉を湯で茹でることで、酸化発酵(紅茶などに見られる発酵)を防ぎ、茶葉の酵素の働きを止めることができます。さらに、余分な渋みを和らげ、阿波晩茶特有のまろやかで優しい味わいの基礎を作ります。
はなぜんでは、最適な時間と温度を調整しながら茹でることで、均一な仕上がりを追求しています。この工程を丁寧に行うことで、次の「擦り」の工程で茶葉に傷をつけやすくなり、発酵の促進にもつながります。
4.擦り

4.擦り
「擦り」の工程では、茶葉を専用の機械で揉み込むことで、表面に細かな傷をつけます。
茶葉に傷をつけることで、次の漬け込み・発酵の段階で乳酸菌が内部に入り込みやすくなり、発酵が均一に進むようになります。この工程の加減が、阿波晩茶の風味を大きく左右するため、力の加え方や擦る時間にも細心の注意を払います。
はなぜんでは、丁寧に擦りの工程を行い、発酵が最適に進むよう調整しています。このひと手間が、阿波晩茶特有のまろやかさと酸味を生み出す大切なポイントとなります。
5.漬け

5.漬け
擦りの工程を終えた茶葉は、大きな桶に詰め込み、上から圧力を加え漬け込みます。この漬け込みの工程は、阿波晩茶の発酵を促す重要なプロセスです。
茶葉がしっかりと水に浸かるように重石をのせ、空気に触れない状態を作ることで、乳酸菌が活発に働きやすい環境を整えます。この状態で約7~9日間じっくりと漬け込むことで、茶葉の中で乳酸発酵が進み、阿波晩茶ならではのやわらかな酸味と独特の風味が生まれます。
はなぜんでは、発酵が均一に進むよう、温度管理や漬け込み期間を調整しながら丁寧に管理しています。伝統的な技法を守りながらも、品質の安定を追求し、より美味しい阿波晩茶を作り上げています。
6.発酵

6.発酵
いよいよ阿波晩茶ならではの乳酸発酵が本格的に進む段階に入ります。桶の中では、茶葉に付着した乳酸菌が増殖し、じっくりと発酵が進んでいきます。
発酵の進み具合は、気温や湿度によって変化するため、管理が非常に重要です。温度が高すぎると発酵が進みすぎて酸味が強くなり、逆に低すぎると発酵が十分に進まず、味わいが弱くなってしまいます。そのため、はなぜんでは漬け込みの環境を細かく調整しながら、最適な発酵状態を維持しています。
この発酵の工程によって、阿波晩茶特有のまろやかな酸味と、爽やかな香りが生まれます。自然の力を活かした発酵の妙が、阿波晩茶の味わいを深め、唯一無二の個性を引き出していきます。
7.撹拌と一次乾燥

7.撹拌と一次乾燥
十分に発酵が進んだ茶葉を桶から取り出し、茶葉を丁寧に撹拌します。漬け込みの間に茶葉が密着していた部分をほぐし、発酵のムラをなくすことで、風味のバランスを整えます。
その際、温風を用い一次乾燥も同時に行います。茶葉に含まれる余分な水分を飛ばし、葉を一枚一枚剥がすのがこの工程の目的です。そうすることで、次の二次乾燥へスムーズにつなぐ事ができるのです。
はなぜんでは、乾燥の温度や時間を細かく調整しながら、この工程を進めています。発酵の風味を最大限に引き出しながら、茶葉の品質を保つために、細心の注意を払っています。
8.二次乾燥

8.二次乾燥
一次乾燥を終えた茶葉は、さらに水分を飛ばすために二次乾燥の工程へと進みます。この工程では、茶葉の水分量を適切に調整し、発酵の風味を閉じ込めながら、長期保存に適した状態へ仕上げていきます。
はなぜんでは、従来の天日干しではなく、専用の乾燥機を使用して茶葉を乾燥させています。これにより、虫やチリ、ホコリの混入を防ぎ、衛生的に仕上げることができます。また、乾燥の温度や時間を細かく調整することで、茶葉の風味を損なうことなく、均一な品質を保つことが可能になります。
この二次乾燥の工程を経ることで、阿波晩茶特有の爽やかな香りとまろやかな酸味が安定し、より美味しい状態へと仕上がっていきます。
9.三次乾燥

9.三次乾燥
二次乾燥を終えた茶葉は、最後の仕上げとして三次乾燥の工程へと進みます。この工程では、茶葉の水分をさらに安定させ、長期保存が可能な状態に仕上げます。
はなぜんでは、ここでも専用の乾燥機を使用し、衛生的な環境のもとで丁寧に仕上げを行います。茶葉の水分が均一になるよう、乾燥時間や温度を調整しながら、最適な状態へと導きます。
この最終乾燥を経ることで、阿波晩茶は香り高く、風味がしっかりと閉じ込められた状態になります。ここまでの工程を経て、ようやく阿波晩茶としての個性が完成し、次の粉砕工程へと移ります。
10.粉砕

10.粉砕
三次乾燥を終えた茶葉は、最後の仕上げとして粉砕の工程に入ります。阿波晩茶は、一般的な茶葉と異なり、比較的大きな葉のまま発酵させるため、そのままだとお湯に成分が十分に抽出されにくいという特徴があります。
そこで、はなぜんでは専用の粉砕機を使用し、適度な大きさに砕くことで、茶葉の断面積を増やし、成分を効率よく抽出できるようにしています。この工程によって、阿波晩茶ならではの爽やかな酸味やまろやかな風味をしっかりと引き出すことが可能になります。
また、粉砕することで茶葉の形状が均一になり、淹れたときの味のブレを最小限に抑えることができます。こうして、飲みやすく、安定した品質の阿波晩茶が完成へと近づいていきます。
11.選別

11.選別
粉砕を終えた茶葉は、最後の工程である選別に入ります。この工程では、茶葉の品質を最終確認し、虫やゴミなどが混入していないかや味の雑味になる部分を取り除くことで、安全性と安定した味わいを実現します。
はなぜんでは、機械ではなく、すべて手作業で選別を行っています。丁寧に人の目で確認し余分な部分を取り除くことで、より高品質な阿波晩茶に仕上げます。
手作業による選別には時間と手間がかかりますが、それこそがはなぜんのこだわりです。こうして仕上げられた阿波晩茶は、豊かな香りと奥深い味わいを持ち、安心して楽しんでいただける一品となります。
こうして、いくつもの丁寧な工程を経て完成するのが、はなぜんの阿波晩茶です。手間ひまを惜しまず、自然の力と人の手で育まれた一杯には、どこか懐かしく、深い味わいがあります。
すべての工程を終えて完成した阿波晩茶の茶葉がこちらです。

この一葉一葉に込められた想いと伝統を、ぜひ皆さまの食卓でも味わってみてください。